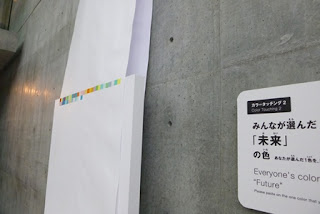練馬にあるアイカ工業東京ショールーム「スペースΦ」が7/1よりリニューアルオープンした。
7/18・19にはオープニングイベントとして、2013ミラノサローネの報告会、2013年新商品発表も開催。
ショールームは毎年商品入れ替えとともに一部リニューアルしており、
今回は新たに店舗市場提案コーナー、女性が提案するトイレ空間(女性目線プロジェクト)を新設するとともに住宅リビングコーナーをリニューアルし、空間全体のコーディネートができるようなショールームとなった。いずれもミラノサローネ2013のトレンドを応用したデザインになっている。
◎リニューアルした住宅リビングコーナー
和テイストの玄関は塗り壁に「ジョリパット爽土」を使用。
リビングダイニングスペースはベースカラーをベージュ・モカ系、アクセントカラーとしてブルー・グリーンを使用したデザイン。壁面戸棚に使用されているブルーは今年のキーカラーでもあるペトロブルー。
キッチンスペースの収納戸棚は、板目柄の新柄メラミン化粧板。
◎店舗市場提案コーナー
カウンターの側面にメラミン化粧版新柄の3D・ホログラムを使用。
光を当てたり見る角度でオーロラ色に変化する。
壁面下部は化粧フィルムオルティノを使用した3次元パネル、上部はローラーパターンのジョリパット。
◎女性が提案するトイレ空間(女性目線プロジェクト)
同社女性社員がプロジェクトを立ち上げ、女性のトイレ空間におけるイメージ調査から商品開発まで行ったもの。写真のパウダールームは、床と化粧台の間につま先を入れられるスペースをつくることで鏡との距離を縮め化粧直しがしやすくなっていたり、荷物置きに角度をつけることで落下防止していたり、細部まで工夫がみられる。
そのほかにも新商品は多々あり。ショールームにて見ることができる。
建築情報サイト『KENCHIKU』http://www.kenchiku.co.jp/ のブログです。建築系コンペ・イベント情報や建築作品等を掲載しています。 新製品情報やコンペ・イベント情報、建築作品等の情報をお待ちしております。 下記メールアドレスまでお送りください。 info@kenchiku.co.jp
2013年7月29日月曜日
2013年7月24日水曜日
デザイナーの喜多俊之氏による、リノベーションの新しい形「RENOVETTA」
数多くのインテリアデザインを手掛けている喜多氏は、日本とイタリアを往復する生活を40年以上おこなっている。
日本とイタリアの環境の違いを見続けた喜多氏は、この問題の根本に日本の住宅の「暮らし」が関係していると考え、住宅をより良い空間に変化させるリノベーションの新しい形「RENOVETTA」を発表した。
喜多氏は「日本とイタリア、それぞれ第二次世界大戦の敗戦国であり、戦後復興を果たした両国で、イタリアは豊かな暮らしの環境を実現したが、日本は経済が発展しても豊かな暮らしの環境を実現できずにいる。
イタリアの住宅は人々の集うサロンであるのに対し、現在の日本の住宅は細かな部屋で区切られ、物があふれ部屋は納戸と化し、ホームインテリアデザインの発達が止まっている。そしてイタリアは優れたインテリアデザインが多い反面、日本はインテリアデザインの発展が止まっていることで、優れた日本国内の伝統工芸や家具製作が危機的状況になっている。
「暮らし」は生活文化と産業経済の土壌。内需拡大は暮らしの現場が良くならないと活気は生まれない。今回発表された「RENOVETTA」は間取りから住まいを見直すプロジェクト。壁で仕切られた部屋の間取りを全て取り払い、部屋の中心に人が集まる空間を設け、豊かな暮らしを実現する」と述べた。
既存のマンションをリノベーションをする際、壁がないことでコストが下がり、市販家具をコーディネートすることで、費用を抑えることが出来、床材等を高価なものにすることも可能。家具はオプションからも選択可能。家具を含めた金額でローンが組めないか検討中。
「RENOVETTA PROJECT」はリビングデザインセンター OZONE 5F 特設会場にて9月24日まで展示中。
ラベル:
design
2013年7月23日火曜日
TOTOギャラリー・間「クリスチャン・ケレツ展 The Rule of the Game」
乃木坂にあるTOTOギャラリー・間にて7/19より「クリスチャン・ケレツ展 The Rule of the Game」が開催中(~9/28まで)。
スイスの現代建築家であるクリスチャン・ケレツ氏、日本初の個展。代表作品として、「フォースター通りのアパートメント(2003)」「壁一枚の家(2007)」「ロイチェンバッハの学校(2009)」などがあげられるが、今回の展覧会では近年取り組んだ5つの設計競技案のみをコンセプト模型と図面、CG画像や映像などで紹介したシンプルな展示構成。
単に美的感覚で生み出されたものではなく、諸々の条件を起点に空間や構造についての検討を繰り返すことによって結びついたデザイン過程の一部を見てほしいとのこと。
3F展示会場
近年取り組んだ3つの設計競技案の展示。
「ホルシム研究開発センター(2008)」
グリット上のスチールの中に数本の円柱を入れたスタディ模型。
円柱を用いて、光の通り道の検証をしたもの。
上の写真の模型を元にスラブの随所に円形の開口をつくり、下の階まで光が落ちている。
「ワルシャワ近代美術館(2006-2012)」
模型、映像のほか、実際のコンペでポーランド政府に提出したビジュアル資料の一部もあり、自由に見ることができる。
他3Fには14階建のオフィスビル「スイス・リー・ネクスト(2008)」の展示がある。
4F展示会場
2つの進行中のプロジェクトの展示。
写真手前は「パライゾポリスの公営住宅(2009–2014)」
「鄭州の高層ビル 第1・2案(2011/2012–2013)」
外部空間に張り巡らされた無数のテンションワイヤーはテントのような考え方でスラブにかかる荷重を配慮した上でこのようなデザインとなった。
展覧会初日は津田ホールにて関連の講演会も行われ、展示会場に展示されている作品の他、実作についての説明もあった。
また今まで手掛けた18作品を掲載した日本初となる作品集「クリスチャン・ケレツ 不確かな必然性(仮)」の発売も決定しており、本のデザインはケレツ氏がおこなった。発売は8月中を予定している。
スイスの現代建築家であるクリスチャン・ケレツ氏、日本初の個展。代表作品として、「フォースター通りのアパートメント(2003)」「壁一枚の家(2007)」「ロイチェンバッハの学校(2009)」などがあげられるが、今回の展覧会では近年取り組んだ5つの設計競技案のみをコンセプト模型と図面、CG画像や映像などで紹介したシンプルな展示構成。
単に美的感覚で生み出されたものではなく、諸々の条件を起点に空間や構造についての検討を繰り返すことによって結びついたデザイン過程の一部を見てほしいとのこと。
3F展示会場
近年取り組んだ3つの設計競技案の展示。
「ホルシム研究開発センター(2008)」
グリット上のスチールの中に数本の円柱を入れたスタディ模型。
円柱を用いて、光の通り道の検証をしたもの。
上の写真の模型を元にスラブの随所に円形の開口をつくり、下の階まで光が落ちている。
「ワルシャワ近代美術館(2006-2012)」
模型、映像のほか、実際のコンペでポーランド政府に提出したビジュアル資料の一部もあり、自由に見ることができる。
他3Fには14階建のオフィスビル「スイス・リー・ネクスト(2008)」の展示がある。
4F展示会場
2つの進行中のプロジェクトの展示。
写真手前は「パライゾポリスの公営住宅(2009–2014)」
「鄭州の高層ビル 第1・2案(2011/2012–2013)」
外部空間に張り巡らされた無数のテンションワイヤーはテントのような考え方でスラブにかかる荷重を配慮した上でこのようなデザインとなった。
展覧会初日は津田ホールにて関連の講演会も行われ、展示会場に展示されている作品の他、実作についての説明もあった。
また今まで手掛けた18作品を掲載した日本初となる作品集「クリスチャン・ケレツ 不確かな必然性(仮)」の発売も決定しており、本のデザインはケレツ氏がおこなった。発売は8月中を予定している。
2013年7月19日金曜日
岩沼「みんなの家」竣工式
インフォコム株式会社が、ITを活用し震災被災地を継続的に支援する目的で宮城県岩沼市に建設していた多目的施設、岩沼「みんなの家」が完成、竣工式が行われた(2013.7.10)
岩沼「みんなの家」は、「みんなの家」活動に共感した中田英寿氏がインフォコムと伊東氏を仲介、特定非営利活動法人がんばッと!!玉浦の方々と協力し実現した。
岩沼「みんなの家」は、1.農業とITの融合により、未来の農業を創出する場、2.若い人たちに地域の農業を継承する場、3.情報の発着拠点として誰もが気軽に集まり、ITを使って農業・食を楽しめる場、として建設された。
伊東氏は「みんなの家の趣旨は、(1)ここを使われる方々が心を通わす場所、(2)みんなで一緒になって考えて、一緒になって作る、(3)これから自分たちのまちをどうするか考える拠点の様な場所。岩沼「みんなの家」は農業をどう新しく再考するか考える人のためのもので(2)や(3)の意味合いが強い。インターネットを活用し、都会の消費者とダイレクトに繋がる新しい農業を興し、農業が素晴らしいものだと発信できる場所になる。」と述べた。
庭の造園費用には、伊東氏の中学時代の恩師である菅沼先生のご遺族や支援企業からの寄付が活用された。
岩沼「みんなの家」では岩沼、玉浦周辺で採れた野菜を販売する予定。
岩沼「みんなの家」は、「みんなの家」活動に共感した中田英寿氏がインフォコムと伊東氏を仲介、特定非営利活動法人がんばッと!!玉浦の方々と協力し実現した。
岩沼「みんなの家」は、1.農業とITの融合により、未来の農業を創出する場、2.若い人たちに地域の農業を継承する場、3.情報の発着拠点として誰もが気軽に集まり、ITを使って農業・食を楽しめる場、として建設された。
伊東氏は「みんなの家の趣旨は、(1)ここを使われる方々が心を通わす場所、(2)みんなで一緒になって考えて、一緒になって作る、(3)これから自分たちのまちをどうするか考える拠点の様な場所。岩沼「みんなの家」は農業をどう新しく再考するか考える人のためのもので(2)や(3)の意味合いが強い。インターネットを活用し、都会の消費者とダイレクトに繋がる新しい農業を興し、農業が素晴らしいものだと発信できる場所になる。」と述べた。
岩沼「みんなの家」は古い民家(農家)を縮小した様な形で、地元の方々による手作りの釜戸や土間があり、ここで食事をしたり、皆が集まりやすく誰でも自由に出入りできる佇まいになっている。
岩沼「みんなの家」の特徴の一つである庭の植栽は中央大学・石川幹子教授の監修で行われた。石川氏は岩沼出身で、復興支援に携わってきた。
建物を囲む緑は、居久根を再現したもの。石川氏は「玉浦地域では農家を北風から守る森・居久根があったが、津波で全て流されてしまった。これからは大きな居久根は出来ないが、幅1m位でも居久根が出来ることを証明し、居久根の再生モデルにしたい。」と述べた。庭の造園費用には、伊東氏の中学時代の恩師である菅沼先生のご遺族や支援企業からの寄付が活用された。
岩沼「みんなの家」では岩沼、玉浦周辺で採れた野菜を販売する予定。
| ■協賛 | ||
| ・株式会社LIXIL | ■設計協力 | |
| ・越井木材工業株式会社 | ・株式会社佐々木睦朗構造計画研究所 | |
| ・チャネルオリジナル株式会社 | ・株式会社エービル | |
| ・セントラル硝子株式会社 | ・中央大学 石川幹子 | |
| ・大光電機株式会社 | ・安東陽子デザイン 安東陽子 | |
| ・元旦ビューティ工業株式会社 | ・株式会社渋谷木材店 | |
| ・株式会社Bb Wood Japan | ■施工協力 | |
| ・田島応用化工株式会社 | ・株式会社熊谷組 東北支店 村岡憲司 | |
| ・フジワラ化学株式会社 | ・渡建 渡辺一申 | |
| ・株式会社タニタハウジングウェア | ・有限会社松建産業 松本一師 | |
| ・グローバル・リンク株式会社 | ・青陽建築設計工房 青陽孝昭 | |
| ・三井化学産資株式会社 | ・有限会社ブルーベリーフィールズ紀伊国屋 松山剛志 | |
| ・城東テクノ株式会社 | ・有限会社ウォーテックヤオヤ | |
| ・株式会社YAMAGIWA | ・特定非営利活動法人がんばッと!!玉浦 | |
| ・渋谷商事株式会社 | ・有限会社やさい工房八巻 | |
| ・フルール花の森 大泉淳子 | ・丸富工業株式会社 | |
| ・エルフの森 岩佐知子 | ・村松建築 | |
| ■協力 | ・一般社団法人茨城県建築士会 | |
| ・株式会社国代耐火工業所 | ・岩沼サポーターズの関係者 | |
| ・株式会社シンコー | ・認定NPO法人ロシナンテス | |
| ・富国物産株式会社 | ・東北大学の関係者 | |
| ・サイレントグリス株式会社 | ・東京大学の関係者 | |
| ・住友林業緑化株式会社 | ・岩沼市の関係者 | |
| ・株式会社ホンマ製作所 | ・岩沼市金曜絆の会 | |
| ・株式会社ユビレジ | ■企画協力 | |
| ・株式会社池商 | ・有限会社和快 | |
| ■資金協力 | ・レコテック株式会社 | |
| ・菅沼家一同 | ・合同会社エイトビー | |
| ・株式会社ニュースト | ・エスピーアール株式会社 | |
| ・アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社 | ||
| ・宮城学院同窓会 | ||
| ・RISTEX(社会技術研究開発センター) | ||
ラベル:
オープンハウス
2013年7月18日木曜日
夢だけど夢じゃなかった 八谷和彦個展「OpenSky 3.0 ―欲しかった飛行機、作ってみた―」
アーツ千代田 3331にて7月13日より、八谷和彦個展「OpenSky 3.0 ―欲しかった飛行機、作ってみた―」が開催している。
これは某アニメに登場する飛行機を実際に作って飛ばそうというプロジェクト。2003年にスタートしたプロジェクトは、グライダーによるゴム索曳航での試験飛行を行い、新たにジェットエンジンを搭載した機体を制作し試験飛行の準備段階にある。
会場にはグライダーM-02とジェットエンジン搭載機M-02Jが展示されている。
M-02
M-02J
シミュレーターではM-02、M-02Jのフライトを疑似体験できる。(体重制限有)
会場内のモニターでは、OpenSkyのこれまでの活動記録や練習風景の動画を上映。これまでの活動を知らない方でも楽しむことが出来る。
会場には飛行機のほか、八谷氏が手掛けたアート作品や、八谷氏が参加している、「なつのロケット団」による「すすめ!なつのロケット団」が展示・開催されている。
「すすめ!なつのロケット団」では、「なつのロケット団」によるロケットエンジンやロケット開発の資料、これまでのロケット打ち上げの記録映像を展示している。打ち上げに失敗した際のロケットの部品等も展示されており、こちらも見所の多い展示となっている。
関連展示として、八谷和彦氏と、天才編み師 203gowによるコラボレーション「momoko×203gow ~coming soon もうすぐ来る世界~」が1Fアートダクトにて展示中。
9月16日まで
2013年7月2日火曜日
カラーハンティング展 色からはじめるデザイン
21_21 DESIGN SIGHTにて藤原大氏ディレクションによる「カラーハンティング展 色からはじめるデザイン」プレスカンファレンス及び内覧会が6月20日(木)に開催された。
中に入ると風鈴の音色が。早速最初の展示。
「夏の音色」篠原風鈴本舗の江戸風鈴につけられた女子美術大学デザイン工学科の学生たちによるインディゴ染めの短冊が、涼しげな音と共にゆれる。
階段を下りて、次の展示会場へ進む。
左には藤原大氏が3月3日に八ヶ岳で色をハンティングしている様子を流したプロジェクター。
右には藤原氏と企画者からのメッセージ。
展示用の色相環の見方やカラーハンティングについて記されている。
カラーハンティングとは、藤原大氏が生み出した自然や都市に存在する現実の色を自ら水彩絵の具を調合してその場で紙片に写し取っていく手法。
順路通りに進むと、おひな様が。
3月3日に霧ヶ峰でカラーハントした色を使って作られている。
ギャラリー1の展示。靴が走り回っている!?
こちらもおひな様のようにアフリカ・タンザニアのセレンゲティ国立公園で、
ライオンの色をハントしてデザインした「ライオンシューズ」。
台の色は現地のマサイ族が住む土地の土の色だという。
ここでも壁面スクリーンには、霧ヶ峰とライオンと土の色のカラーハンティングが投影されている。
ギャラリー2。カラフルな展示品が並ぶ。
「スカイダイアリー」
毎日朝8時から11時までの空の色を、藤原氏が日記のように記録。ずらりとブルーが並ぶ。所々真っ白な何も塗られていない紙がある。出張などでカラーハントできなかった日だという。
「国家珍宝帳」
聖武天皇の遺愛品のリストに記載されている26色のうち12色を展示。
8色は現在作成中で後日追加の予定。
会場の什器はハニカム構造のダンボールが使用されている。
会期終了後は古紙としてリサイクルされる。
自然の色はその時その場の環境によって変わる。
それぞれの土地に地元の色があると藤原氏は語る。
それを納得させてくれるのは「みずいろハンカチ」。
47都道府県の水道水、湧き水や温泉、湖の水を使って全く同じ染料で染めている。
同じ染料でもどこの地域の水を使うかによって色が変わる不思議。
来場者参加型の展示もあり。
「動く色」
メモリの無い温度計に来場者が指をのせ、その人の体温で温度が止まったところにメモリを作るというインスタレーション。マッチ棒のようなカラフルな温度計の横に色鉛筆でメモリを刻む。何色を選んでどこで止まるかはあなた次第。
私も記念に。
「カラーシューティング」
ハンドガン、バズーカなど3種類の電子銃で、壁のキャンパスに思い思いに色を撃つ。発色や重なりを楽しんで。
「遊ぼう!カラータッチング、空想どうぶつえん」
あなたにとって「未来」とは何色ですか?
私の未来はこの色だ!というカラーチップを一つだけ選んで、後ろにあるボードに貼る。
ボードが埋め尽くされたときどんな色になるのか楽しみだ。
会期は10月6日(日)まで。
---------------------------------------------
タイトル:企画展 藤原 大ディレクション
「カラーハンティング展 色からはじめるデザイン」
会期:2013年6月21日(金) - 10月6日(日)
休館日:火曜日
開館時間:11:00 - 20:00(入場は19:30まで)
入場料:一般1,000円、大学生800円、中高生500円、小学生以下無料
---------------------------------------------
ラベル:
event,
exhibition
登録:
投稿 (Atom)